岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
|---|
定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
|---|



| 家系の調べ方編 (1)歴史ロマンを秘める家系調査のすすめ 自分のルーツを知るチャンスは、まだまだ古い戸籍が現存している 今です! まずは戸籍で先祖を200年程たどり、その先は他の史料を探 して調査をすすめていく!(家系図や家系譜はそのための基本資料) ●親族等の関係書類の調査(戸籍の取り寄せ、物故者の位牌・菩提寺で 先祖の事績や墓石・墓誌・過去帳の調査など) ●古記録の調査(検地帳・宗門人別帳・親族の系図・先祖の由緒書・家 の古い記録や古文書など) ●遺物・遺跡の調査(苗字を記されている墓誌・記念碑・神社や寺院の 建造物・石燈篭・石棚・玉垣など) ●家系図・家系譜の作成
(2)先祖を200年以上たどるための史料と所蔵場所について 戸籍以外の調査史料を探して、先祖を200年以上たどる方法は? 見てみたい調査史料の種類と所蔵場所の一部について紹介します! ①武家に関する調査史料(藩士系図・分限帳・一族の系図系譜) ②庶民に関する調査史料(過去帳・旧土地台帳・諸国地誌・郡県市町村 史・宗門人別帳) ③家系調査史料の探し方・所蔵場所
(3)先祖を200年程さかのぼるための戸籍調査について 家系調査のスタートは、200年たどるための戸籍の収集から!
(4)先祖を200年たどる「戸籍調査と家系譜作成」のすすめ 直系尊属一人一人の歴史がわかる「家系譜」は、200年以上先祖をたど るための必要且つ最重要資料! ✅家系調査(戸籍調査)サービスのご案内 ルーツを知りたい方におすすめ!
(5)家族の歴史「家系図作成」のすすめ 家系図で、200年にわたる直系尊属・傍系尊属の全容が、今明らかに! 「家系図」は、菩提寺に「過去帳」の作成を依頼するための必要資料! ✅家系図作成サービスのご案内 家系図を作りたい方におすすめ! ✅無料資料請求はこちら |


ファミリ―ヒストリ―
(1)歴史ロマンを秘める家系調査のすすめ
自分の先祖やルーツを知りたいという思いは、誰でも一度は抱いたことがあるのでは
ないでしょうか。テレビなどで、著名人の家系や子孫についてその全容を見たりして、
今まで特に考えもしなかった自分のル―ツについて急に興味が湧いてきた、という方も
多くいるようです。
ところで、自分のル―ツをたどるには、いろいろな方法があります。
家系調査の基本デ―タとなる戸籍の収集、菩提寺の過去帳の閲覧、先祖が多く眠って
いる墓石の調査、その家代々に伝わる様々な資料の調査、親族で作成した系図の存在の
有無の調査・・・。その過程で、自分の先祖に歴史上の有名な人物がいることを発見す
るかもしれません。
家系調査は、そのような驚きの新事実発見という歴史ロマンを秘めています。
ここで紹介するのは、先祖調査の最も効果的な「戸籍で先祖をたどる方法」です
が、正確に、モレなく入手することで、誰でも確実にル―ツをたどることができます。
戸籍は、ご存じのように、相続関係を証明するためにも必要不可欠とされる書類で
すが、同時に、先祖との関係を公に証明してくれる唯一確かな公文書といえるものです。
現在請求できる戸籍で最も古い戸籍といわれる「明治19年式戸籍」まで入手できる
と、その戸籍には江戸時代の情報も記載されていることが多いので、150年~200
年程度、先祖をたどることができます。
なかには、収集した戸籍から、230年前、7代前のご先祖様が判明したというケース
もありますので、まずは最古の戸籍まで正確にたどって請求してみましょう。
また、その家代々に伝わる古文書や過去帳などを綿密に調査した結果、戸籍に記載され
た先祖の名前が発見され、そこから、順に直系尊属の名前をたどって調べた結果、江戸時
代の初期まで判明したということもあります。

家系調査のスタートは、このように、戸籍・除籍謄本の取り寄せから始まりますが、
プライバシー保護の観点から、戸籍を請求できる人は、その戸籍に記載されている者及
びその配偶者、直系尊属又は直系卑属に限られています。叔父・叔母などの傍系尊属や、
甥・姪などの傍系卑属の戸籍は請求することができませんので限られた範囲になってし
まいます。叔父や叔母の戸籍を請求するためには、その子(従弟従妹)や孫に当たる方
の委任状が必要となります。委任状を書いてもらうことができれば傍系尊属(叔父・叔
父・大伯父・大叔母など)や傍系卑属(従弟や甥・姪など)についても戸籍を請求して
調査することは可能ですので、その場合は、ご親族の方などから聞き取り調査を行いな
がら「委任状」を書いてもらえる方を探して依頼してみましょう。
直系とは、親子の関係が続く系統のことで、実親、養親、実子、養子を問いません。
直系尊属とは、父母、祖父母などのように、血統が親子の関係で続いていて、親等上、
父母と同列以上にある血族のことをいいます。
これに対して、直系卑属とは、子や孫などのように、血統が親子の関係で続いていて、
親等上、子と同列以下にある血族のことをいいます。
先祖を調べる上で最も重要な「除籍簿」には、法律で定められた保存期間がある!
死亡、結婚、他の地域への転籍などの理由によって、全員が戸籍から除かれた場合、
その戸籍は除籍となり、除籍簿として別に管理されることになりますが、この除籍簿は、
150年(法定保存期間)を過ぎてしまうと、各役所の意向で廃棄処分してもよいこと
になっていますので、除籍された戸籍が残っているか否かは実際に請求してみなければ
わからないというのが実情です。
一部の大都市や県庁所在地、戦災・災害で戸籍が焼失した地域の役所を除き、最古の
戸籍まで残っているところが圧倒的に多いのですが、役所の意向により、150年経過
と同時に処分される可能性もありますので、いつかは戸籍よりさらにさかのぼって先祖
を調べてみたいと思っている方には、早めに戸籍を取得しておくことをおすすめします。
廃棄された戸籍は、永久に請求することができない!
最古の戸籍まで入手するためには、廃棄対象となる前に請求する必要がありますが、
現存しているか廃棄になっているかは、必要としているその役所に請求してみなければ
わからないのが実情です。
もしかしたら、自分の代で戸籍を取っておくことが、最古の戸籍まで入手できる最後
のチャンスかもしれません。
このようにして現存する最古の戸籍まで入手できれば、少なくとも150年程度前まで
先祖をたどることができますが、廃棄処分されていたり、戦災や大火により戸籍の焼失
がなければ、他の史料を探すことで、さらに先祖をたどれる可能性が高くなってきます。
200年~220年以上前の先祖の情報を知りたい方は、次に紹介する参考史料を探しなが
ら調査を進めてみることをおすすめします。
先祖をどこまでも辿るために見ておきたい史料は、下記に紹介した他にも無限にあり
ます。
特に、「戸籍上で判明した最古の本籍地」は、自分のルーツを知るための史料の宝庫と
言われています。新しい発見のため、見てみたい史料の種類や所蔵されている場所を事前
に調べるなど、周到に準備した上で、訪ねてみてはいかがでしょうか。
(2)先祖を200年以上たどるためにぜひとも見ておきたい調査
史料とその所蔵場所について
●武家のルーツを調べたい場合
①藩士系図(所蔵場所の一例)家臣団の系譜
秋田藩士系図(県立秋田図書館)
南部家臣系譜(岩手県立図書館)
伊達世臣家譜(宮城県立図書館)
世臣譜(新発田藩)(県立新潟図書館)
当邦諸侍系図(加賀)(石川県立図書館)
紀州徳川藩士系図(和歌山県立図書館)
岡山藩士奉公書(池田家文庫~岡山大学図書館内)
家譜(鳥取藩)(鳥取藩政文庫~鳥取県立図書館内)
萩藩「閥閲録」(山口県立史料館)
水口藩士先祖系譜録(愛媛県立図書館)
徒歩以上苗字類中興系図(高鍋藩)(宮崎県立図書館)
他については、旧藩もよりの県立図書館に「藩士系図」の有無について尋ねてみる。
②分限帳(所蔵場所の一例)
✅藩士の姓名や石高を記した藩士名簿(分限帳)も、家系調査の重要な史料!
どこの藩でもあるというわけではなく、県郡市町村史に収録されていることも
あり!
✅国立国会図書館では全国的に分限帳を収集している!
元禄年中御家中分限帳(津軽藩)(市立弘前図書館)
正保四年分限帳(米澤藩)(市立米沢図書館)
酒井下野守様分限帳(館林藩)(群馬県立図書館)
堀田家佐倉藩士定録人名表(千葉県立中央図書館)
松代藩御家中分限帳(県立長野図書館)
尾州分限帳(名古屋)(名古屋市立舞鶴中央図書館)
倉藩知行録(福岡)(福岡県立図書館)
亀山藩士族家録帳(三重県立図書館)
分限帳(竜野藩)(兵庫県立図書館)
松江藩給帳(島根県立図書館)
讃岐髙松藩分限帳(髙松市立図書館)
➂地域的「一族の系図」「氏族の系譜」(所蔵機関の一例)
〇一族の系譜・系図の例
「新田族譜」(群馬県立図書館)※新田氏一族
「田原族譜」(栃木県立図書館)※藤原秀郷の子孫全体の系図集
その他については、国立国会図書館や各氏族発祥地の公共の図書館で探してみる!
〇地域的な系譜他関連史料
常総名族系譜集成(茨城県立図書館)
諏訪郡諸家系譜(県立長野図書館)
誠忠旧家録伝(山梨県立図書館)
濃陽諸士伝記(名古屋市立舞鶴中央図書館)
加越能氏族伝(石川県立図書館)
土佐名家系譜(高知県立図書館)
諸家大概(鹿児島県立図書館)
〇個人別系譜
個人別系譜については、地方の郷土史家が収録しているものがあり、各県立図書
館や史料館に残されている。
どこに何かあるかは、各図書館の「郷土史料目録」を見て探してみる!
④他自刊本・姓氏史料復刻版(明治・大正)の一例 個人の系譜
信濃史源考(小山愛司書)
彦根藩士族譜(中山達夫書)
芸藩輯要ー藩士家系名鑑(村保登書)
石見諸家系図録(岡本正司書)
三州諸家系図桟纂(鹿児島・川崎大十書)
土屋氏族の系譜(土屋政一書)
村上百系図(村上一族の歴史の会)
石原家類代系図(伊勢崎・矢内薫書)
他については、出身地の図書館に寄贈されていることが多いので、もよりの
図書館へ照会して探してみる!
●庶民のルーツを調べたい場合
①過去帳 ~菩提寺と家(仏壇のある実家など)の両方にある!
代々の死者の戒名(法名)・俗名・没年齢・没年月日(日別と死亡順)・続柄が記
載されているが、俗名や続柄が省略されていることもあり、親子・夫婦・兄弟の
関係がわからないこともある。このような場合は、他の資料や墓石、墓誌、位牌
の戒名を読むなどして不明な点を推察していく必要があるが、先祖の名前や死亡し
た時代がわかるので、家系を調べる上で一等資料と言えます。
②旧土地台帳 ~各地の法務局に保管されている(閲覧無料)!
最古の戸籍の「本籍」で旧土地台帳を閲覧、土地の所有者などがわかる。
土地を所有した理由(相続など)が記載されていますので、現所有者の親から
相続で取得した土地であれば、さらに一代前の先祖の名前が判明したことになり
ます。この台帳に記載されている最初の所有者は、明治20年代初期の土地の
所有者(その時代の当主)になりますので、幕末の時期に生まれた方と推定する
ことが出来ます。
③諸国の地誌 関係土地の方は必見の史料
●風土記(江戸時代)の一例
✅当時の郡郷ごとに地名由来や産物・社寺・伝承について記載されている!
✅当時の郡・村の状況、物産、歴史、人物詩などについて豊富に収録され、
武士や農民をとわず参考になる!
奥羽(会津家世実記、白河風土記、秋田風土記、仙台封内風土記、津軽一統志、
磐城史料)
関東(上野国志、新編常陸国志、新編武蔵国風土記稿、新編相模国風土記稿、
御府内備考)
中部(駿国雑志、甲斐国志、三河志、越後野志、若狭志略、新編美濃志、尾張志)
近畿(紀伊続風土記、丹波志、播磨鑑、近江与地志略、摂陽群談、五畿内志)
中国(備中集成志、吉備温故作州記、伯耆志、雲陽詩、芸藩通史、長防風土記)
四国(阿波志、全讃志、讃州府志、西讃府志、讃岐志、愛媛面影、南路志(土佐)
九州(豊後国志、豊前志、筑前国続風土記、日向地誌、肥後国志、大隈史料)
●他、家蔵文書、古記録、宗門人別改帳、検地帳など
④県郡市町村史 市町村史は様々な史料の宝庫
全国のほとんどの地方自治体にて編纂されているので、ご先祖ゆかりの町村史は
通史から古文書まで様々の地域史料が豊富!
「県郡市町村史」の中には、系図編があり民間諸家系図が多く収録されているもの
もある!
市町村史は地域史料の調査には欠かすことはできません。郷土史家が中心になって
史料の探索、整理、執筆を行っています。先祖ゆかりの町村史は、古文書・系図・
姓氏についても詳細に記載されています。
県郡史は、県・郡教育委員会などによって編集されています。県史は、各時代ごと
に通史・史料編・考古学・民族関係などについて分冊されていることも多く、特に、
系譜・氏族・社寺・町村の古文書・分限帳など、藩政史料が広く収録されています
ので、ぜひ見ておきたい史料と言えます。 また、大正から昭和初期にかけて各地方
の古典的文献を集成した叢書には、地方の古文書・記録が収録され、社寺史料・系
図・石高帳・地詩・分限帳などが収められ、各県立図書館に所蔵されています。
≪ 県郡史の例 ≫
①札幌区史 ②西津軽郡史 ③宮城県本吉郡史 ④長野県下水内郡詩 ⑤三重県史
⑥兵庫県加古郡郡詩 ⑦岡山県邑久郡詩 ⑧香川県仲多度津郡詩 ⑨高知県史要
⑩熊本県菊池郡詩
≪ 系図編の独立刊行例 ≫ 民間諸家系図が数多く収録されている!
➀「埼玉県史」(年表と系図) ②「えびの市史」(系図編)
≪ 市町史の例 ≫
系譜・氏族・社寺・町村古文書・分限帳などを含む藩政史料が広く収録されている!
①「結城市史」 ②「大滝村詩」(埼玉県) ③「古河市史資料」④「西尾市史」
⑤「昭和町史」(山梨県) ⑥「山形市史資料」 ⑦「芳野村郷士詩稿」
⑧「所沢市史研究」
⑤宗門人別改帳 キリシタン禁止のために設けられた現在の戸籍のようなもの
県立図書館にあったり、県市町村史に収録されていることもあるが、全国的に
は多くない!(各県の機関に照会する)
高持百姓・水呑百姓・家持の本町人・店借の町人の別なく記載されているので貴重
な史料といえる。戸主以下家族の名前・年齢・所属寺院・女房の実家や結婚年月日・
娘の嫁ぎ先まで記載されているものもある。
≪ 宗門人別改帳の例 ≫
県市町村史の中で史料編として収録されているものもある!
〇小沼村宗旨人別改帳(山梨県立図書館)
〇桑戸村宗門御改帳(同)
〇青木村常光寺宗旨証文(同)
〇切支丹御改五人組帳(彦根安養寺町)(滋賀県立図書館)
〇切支丹宗門改帳(禅宗分)(同)
〇香川郡中村切支丹宗門御改帳(髙松図書館)
〇香川郡笠居村切支丹宗門御改帳(同)
〇香川郡東村切支丹宗門御改帳(同)
⑥地域の人物研究のための文献
各県立図書館には明治・大正期の人物録や人名録が所蔵されています。祖父や
高祖父で地域振興に関係のある人物なら、中央では知られていなくても地域的
には記録されている可能性がある!
〇「開拓功労者事蹟 北海道庁」(函館)
〇「盛岡藩贈位者伝」(岩手)
〇「上州人物史 明治28」(群馬)
〇「百家名鑑 明治37」(千葉)
〇「新潟県地下特姓名録 明治25」(新潟)
〇「戸長名鑑 明治12」(岐阜)
〇「石川県の華 明治43」(石川)
〇「大阪府職員録 明治16以降」(大坂)
〇「勝南郡各村吏履歴書 明治5~10」(岡山)
〇「日露戦役土佐武士鑑」(高知)
〇「島原人物詩 明治42」(長崎)
<地域的人名辞典>
〇青森県人名辞典
〇仙台人名大辞典
〇上野人物志
〇越佐人物詩
〇島根県人名辞典
〇近世防長人名辞典
〇高知県人名辞典
〇大分県人物志
●家系調査史料をどこで調べるか? どこにあるか?
①県立図書館・市町村立図書館・史料館・文書館・教育委員会
図書館の「郷土史料目録」を活用することが効果的(特殊文庫や研究機関にもあり)
図書館に無い場合は、類縁機関を紹介してもらい訪ねる!(どこの図書館でも、関係
する諸機関と連携しているので紹介してもらう。類縁機関名簿を発行している図書
館もある)
〇系図文献~武家系図・藩士系図・分限帳・総合系図集・地域的氏族譜・同族系譜・
家伝系図など
〇地方文献~県郡市町村史・県史編纂史料・地誌・旧国叢書など
〇古文書~宗門人別改帳・検地帳・家蔵文書・村方古文書・町方古文書・武家
古文書・戸長古文書まど
〇人名辞典~姓氏辞典・地域人名辞典・人物詩・人物録など
※図書館に、電話・郵便で史料を請求することも可能!
「〇〇藩士であった先祖の系図あるいは〇〇藩に関する参考文献を知りたいので、
ありましたらお知らせ下さい」
「〇〇藩士〇〇姓の系譜・由緒書を探していますので、ありましたらお知らせ下
さい」
「発祥地は〇〇県の〇〇村であり、〇〇村に関する地誌的史料等から自家のこと
を知りたいと思っているので、参考文献がありましたらお知らせ下さい」
②図書館に併設してある「文庫」を活用
学者・文化人などが藏書を寄贈・寄託したり、藩士秘蔵文書・記録を委託して保管
整理している機関
<家系調査に関する文庫>
1.県立秋田図書館(佐竹文庫)
2.宮城県立図書館(伊達文庫)
3.市立米沢図書館(上杉文庫)
4.東京都立中央図書館(加賀文庫)
5.金沢市立図書館(加越能文庫)
6.福井県立図書館(松平文庫)
7.広島県立図書館(浅野文庫)
8.愛媛県立図書館(伊予史談会文庫)
9.内閣文庫(東京都千代田区)
※国立公文書館内にあり、幕府が保管した蔵書52万冊を閲覧できる
10.尊経閣文庫(東京都目黒区)
11.金沢文庫(神奈川県横浜市)
12.蓬左文庫(愛知県名古屋市)
13.鬼洞文庫(大坂府岸和田市)
(3)先祖を200年程さかのぼるための戸籍調査について
家系調査のスタートは、先祖を200年たどるための戸籍の収集から!
戸籍調査で家系を調べる場合、まず、どの系統の先祖を調べるか、その範囲を決めて
戸籍を取る必要があります。
例えば、父方・母方の全部の家系を調べる場合、下記の通り、それぞれ8家系の調査
が考えられます。
直系尊属の父・祖父・祖母・曾祖父・曾祖母等が養子の場合は、その実父と実母の家
系がさらに増えることになります。
≪ 父方の例 ≫
➀父の父(祖父)の家系
➁父の父(祖父)の母(曾祖母)の家系
➂父の父(祖父)の父(曾祖父)の母(高祖母)の家系
④父の父(祖父)の母(曾祖母)の母(高祖母)の家系
➄父の母(祖母)の父(曾祖父)の家系
⑥父の母(祖母)の父(曾祖父)の母(高祖母)の家系
⑦父の母(祖母)の母(曾祖母)の父(高祖父)の家系
⑧父の母(祖母)の母(曾祖母)の母(高祖母)の家系
≪ 母方の例 ≫
①母の父(祖父)の家系
②母の父(祖父)の母(曾祖母)の家系
③母の父(祖父)の父(曾祖父)の母(高祖母)の家系
④母の父(祖父)の母(曾祖母)の母(高祖母)の家系
⑤母の母(祖母)の父(曾祖父)の家系
⑥母の母(祖母)の父(曾祖父)の母(高祖母)の家系
⑦母の母(祖母)の母(曾祖母)の父(高祖父)の家系
⑧母の母(祖母)の母(曾祖母)の母(高祖母)の家系
【調査範囲を定めた戸籍の取り方の例】
■父方の①自分の苗字に繋がる先祖を調べたい場合
(自分の父の苗字を称している場合)
基本的に、次の順序で戸籍を請求していきます。
➀戸籍筆頭者(又は戸主)が父の戸籍
↓
➁戸籍筆頭者(又は戸主)が父の父(祖父)の戸籍
↓
➂戸籍筆頭者(又は戸主)が父の父(祖父)の父(曾祖父)の戸籍
苗字を基本としてさかのぼっていきますので、必ずしも父方が同じ苗字であると
は限りません。祖父が祖母の父(又は母)の養子となっている場合があります。
このような場合は、苗字が同じ祖母の父(又は母)が戸籍筆頭者(又は戸主)の
戸籍を請求します。
また、祖父祖母ともに養子になって結婚している場合もあります。
この場合は、祖父と祖母の養父(又は養母)が戸籍筆頭者(又は戸主)の戸籍を
請求するようにします。
注意しなければならないのは、戸籍をさかのぼって請求していく過程で、直系尊
属(父母・祖父母・曾祖父母など)が必ずしも戸籍筆頭者や戸主となっていない場
合がありますので、入手した戸籍から前の戸籍の筆頭者(又は戸主)が誰なのか、
そして本籍地がどこになっているのか、注意深く見る必要があります。
直系尊属が戸主となっていないケースとしては、直系尊属(例曾祖父)が隠居し、
長男が戸主となり、その戸籍に二男の祖父が入っている場合があります。
このような場合は、祖父の兄が戸主となっている戸籍を請求します。
前戸主が死亡や隠居したことにより相続し戸主となった場合は、「本籍」は同じに
なりますので、さかのぼるためには、同じ本籍地で、前戸主(又は筆頭者)の戸籍を
請求します。
また、婚姻届時に親が亡くなっていたために、傍系尊属(例兄)が戸主(又は筆頭
者)となっている場合もあります。この場合は、戸主(又は筆頭者)名が兄の戸籍を
請求します。
いずれにしても、戸籍には「戸主又は筆頭者」と「本籍地」を示す記載が必ずあり
ますので注意深見てください。
このように、戸籍を請求するためには、戸籍筆頭者名(又は戸主名)の記載が欠か
せませんので、新しく戸籍がつくられた原因と、誰の戸籍から新しい戸籍に入籍して
いるか注意して見る必要があります。
また、転籍によって本籍地が変わったり、法改正などによっても新戸籍編製が行わ
れますので、この点についても注意深く見ていかなければなりません。
さかのぼっていく途中で一つでも戸籍がモレてしまうと、大事な情報が抜け落ちて
しまうことがありますので、必ず前後の戸籍がつながっているか確認しながら請求す
ることが大切です。
中でも、法改正により新しく戸籍がつくられている場合は、必ず、改製原戸籍を請
求してください。
■父方の⑤父方の祖母の旧姓に繋がる先祖を調べたい場合
(父方の祖母が、父・曾祖父の苗字を称している場合)
➀戸籍筆頭者(又は戸主)にが父の戸籍
↓
➁戸籍筆頭者(又は戸主)が父の父(祖父)の戸籍
↓
➂戸籍筆頭者(又は戸主)が父の母(祖母)の父(曾祖父)の戸籍
という順序で戸籍を請求していきます。
■母方の①母の旧姓に繋がる先祖を調べたい場合
(母が、自分の父・祖父の苗字を称している場合)
➀戸籍筆頭者(又は戸主)が父の戸籍
↓
➁戸籍筆頭者(又は戸主)が母の父(母方の祖父)の戸籍
↓
➂戸籍筆頭者(又は戸主)が母方の祖父の父(曾祖父)の戸籍
という順序で戸籍を請求していきていきます。
■母方の⑤母方の祖母の旧姓に繋がる先祖を調べたい場合
(母方の祖母が父・曾祖父の苗字を称している場合)
➀戸籍筆頭者が父の戸籍
↓
➁戸籍筆頭者(又は戸主)が母の父(祖父)の戸籍
↓
➂戸籍筆頭者(又は戸主)が母方の祖母の父(曾祖父)の戸籍
という順序で戸籍を請求していきます。
現在のところ、戸籍・除籍謄本の取得によって、平均すると4代〜5代先まで判明
するケ―スが多いのですが、明治時代の戸籍が入手できれば、その戸籍には江戸時代
の情報が記載されていることが多いので、時には、先祖を200年以上さかのぼれる
場合もあります。
古い戸籍を取ってみるとわかりますが、一つの戸籍にたくさんの名前が載っている
ことがあります。高祖父母や曾祖父母の直系尊属やその兄弟姉妹(傍系尊属)とその
子供や孫まで、合わせて50人以上になることもあり、このような戸籍を見ると当時
の大家族の様子まで感じられ、大変興味深いものがあります。
廃棄処分がすすんでいる現在においても江戸時代後期位までは、戸籍で先祖の情報
を知ることができますが、現存している除籍簿も、いずれは各市町村の意向次第で、
廃棄処分の運命にあることを考えると、先祖調査は思い立った時が最後のチヤンスと
いえるかもしれません。(除籍簿の法定保存期間は150年)
戸籍以外にも先祖をたどる方法はいろいろありますが、確実に先祖を、150年~
200年たどるためには、戸籍は必要不可欠な存在です。戸籍は、役所の意向により
廃棄処分にされてしまうと永久に請求できませんので、200年以上さかのぼることは
非常に困難になってしまいます。いずれは先祖をたどって調べたいと思っている方には、
お早めに戸籍を取っておくことをおすすめします。
(4)先祖を200年たどる「戸籍調査」のすすめ
“歴史ロマンを秘める”先祖をたどる戸籍調査と家系譜作成
先祖に関する貴重な資料や古い戸籍が次第に失われていく昨今、今こそ先祖の歴史
を紐解き、江戸時代から連綿と命をつないでくれた我が家の先人達に想いを馳せてみ
ませんか?
先祖をたどる上で必要不可欠な古い戸籍は、法定保存期間150年経過で廃棄対象と
なり、各役所の意向で、いつ処分されてもおかしくない状況になります。
一度廃棄処分された戸籍は永久に請求することができませんので、戸籍だけで先祖
を150年以上たどることが、ほとんど不可能になってしまいます。もちろん、戸籍以外
の史料を探して先祖をたどることは可能ですが、150年以上さかのぼるためには、戸籍
と他の史料との接点を探ることになりますので、戸籍は必要不可欠な存在と言えるも
のです。
このため、時間をかけて、どこまでも先祖をたどってみたいと思っている方には、
“古い戸籍が多く残っている今のうち”に戸籍を収集しておくことをおすすめする理由
がそこにあります。
そして、古い戸籍まで入手できましたら、今後さらに先祖を辿っていく基礎資料と
なる「家系譜」や「家系図」を作っておけば、いつかは過去帳や他の史料との接点を
探るための重要な資料となります。
200年たどる戸籍調査の後で、さらに先祖をたどってみませんか?
収集した戸籍や、作成した「家系譜」や「家系図」を用意して、戸籍上で判明した
最古の本籍地を訪ねてみてはいかがでしょうか。
「最古の本籍地」は、先祖を200年以上たどるための史料の宝庫と言われています。
先祖が多く眠っている菩提寺の過去帳や墓石、墓誌、位牌などを見たり、地元の図書
館や史料館、文書館には旧町村時代の史料が豊富に遺されていることが多いので、これ
らの史料から「家系譜」や「家系図」との接点を探ることができます。
「最古の本籍地」にある各種の史料を探しながら調査するには、費用も時間もかかり
ますが、「最古の本籍地」は貴方の先祖の「発祥の地」です。
新しい発見のため、タイミングを見ながらお訪ねになってみてはいかがでしょうか。
“先祖の戸籍を収集し「家系譜」を作成する”
全国対応 先祖調査サービス
調査家系実績 9000家系超(令和6年末)
□先祖供養をしたいと思っている方におすすめ!
□自分のルーツを知りたいと思っている方におすすめ!
□我が家の歴史を後世に伝えたいと思っている方におすすめ!
□両親に「家系譜」をプレゼントしたいと思っている方におすすめ!
【 家系譜作成費用の例 】 リーズナブルな費用が好評!
●戸籍収集+家系譜作成コ―ス ※1家系~全家系調査まで
1家系調査 22,000円+戸籍代(実費)
2家系調査 40,000円+戸籍代(実費)
全家系調査 120,000円(父方母方全家系)+戸籍代(実費)
※戸籍収集のみ希望の方にも対応! (費用の詳細は資料でご確認ください)

(5)我が家の歴史「家系図作成」のすすめ
ファミリーヒストリー
家系図は、日本で、そして世界中で静かなブームとなっています。
古い戸籍が残っていれば、今でも戸籍の調査で先祖を200年程さかのぼるこことが
可能です。
200年の我が家の歴史を後世に伝えるためにも、また、自分のルーツをさらにたどる
ためにも、我が家の歴史「家系図」を作りませんか?
先祖を200年以上たどるための一等史料と言われている「過去帳」を見て、さらに
1代前~数代前の先祖にあたるか否かを判断する上でも「家系図」は重要な資料です。
過去帳以外にも、先祖を200年以上たどるために見ておきたい史料はたくさんありま
すので、「家系図」を作られましたら、実地調査(菩提寺の過去帳、お墓、墓誌、位牌
など)や文献調査(自家所蔵文献、系図文献、郷土史、分限帳、郡町村史詩など)、親
族などからの聞き取り調査を行って、さらに100年~200年程先祖を辿ってみてはいか
がでしょうか。
このように、「家系図」は、後世に先祖の歴史を伝えるという目的の他に、さらに
先祖をたどる上で、他の史料との接点を探るための必要不可欠な資料となりますので、
古い戸籍が残っているうちに、自分の代で「家系図」を作られることをお勧めいたし
ます。
“先祖が生きてきた時代背景が詳しくわかる”
全国対応 家系図作成サ―ビス
作成実績 1800名様超(令和6年末)

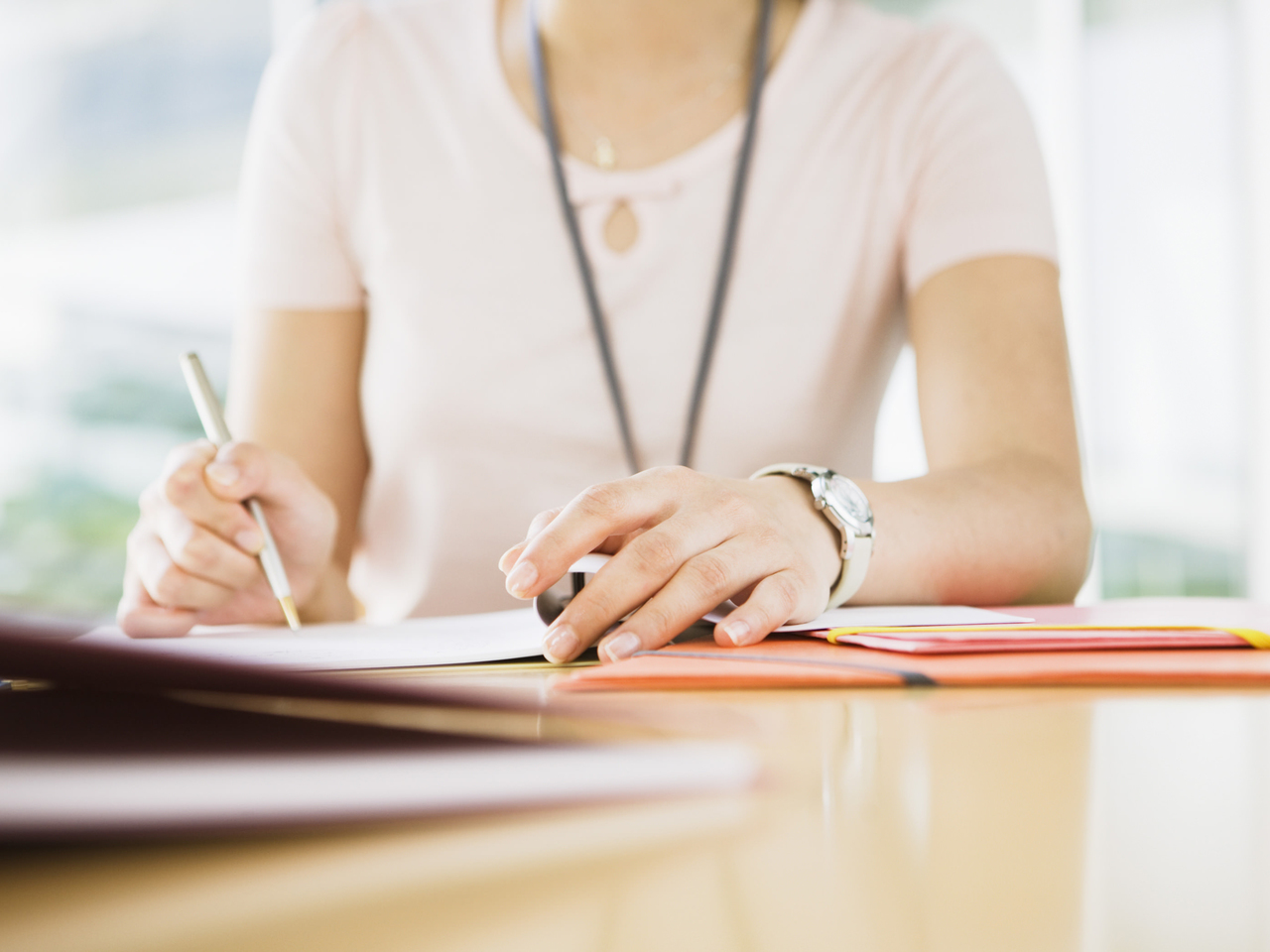
✅プロのグラフィックデザイナーが作成する「デザイン家系図」が大好評
□繊細で美しいデザイン、先祖の歴史の重みが感じられる家系図!
□先祖が生きてきた時代背景が詳しくわかる、世相まで感じられる家系図!



お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ
<受付時間>
AM9:00~PM6:00
※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します
メールマガジン登録フォーム
フォーム準備中