岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
|---|
定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
|---|
贈与税の基礎知識
1.贈与税のしくみ
2.贈与財産の課税価格
3.贈与税の課税方式〜暦年課税と相続時精算課税
注意:(法改正)2つの制度は2024年1月から変わる!
4.贈与税の納税義務者
5.贈与による財産の取得時期について
6.贈与税のかかる財産・かからない財産
7.贈与税の申告と納税

1 贈与税のしくみ
贈与税は、個人が個人から財産をもらったときにかかる税金です。その年の1月1日
から12月31日までに受けた贈与財産の合計額に課税される「暦年課税」の方式(通
常の贈与)が一般的ですが、贈与を受けたときに贈与税を申告・納付して、贈与者が
死亡した時に相続税の申告をして精算する「相続時精算課税」の課税方式を選択するこ
ともできます。
贈与とは、当事者の一方が自分の財産を無償(タダ)で相手方に与える意思表示をし
て、相手方がこれを承諾することによって成立する契約の事をいいます。
贈与契約は、「私の財産をあげましょう」「もらいます」という口約束だけで成立し
ますが、書面によらない口約束だけの場合
は、各当事者は履行が終わっていない部分についてはいつでも取り消しできます。従っ
て、口約束のトラブルを避けるためには、きちんと、「贈与契約書」をつくる必要があ
ります。
尚、書面で贈与契約をした場合には、原則として、撤回することはできないとされて
います。

2 贈与財産の課税価格
贈与財産の課税価格は、相続税と同じ相続税評価額で計算して出します。
評価方法
| 財産 | 評価方法 |
| 宅地 | ① 路線価方式(市街地にある宅地) ② 倍率方式(郊外地や農村部の宅地) |
| 農地 | 純農地、中間農地、市街化周辺農地、市街地の別により ① 倍率方式 ② 比準方式 |
| 山林 | 純山林、中間山林、市街地山林の別により ① 倍率方式 ② 比準方式 |
| 借地権 | 宅地の評価額 × 借地権割合 |
| 貸宅地 | 宅地の評価額 × 借地権価額 |
| 家屋 | 固定資産税評価額 |
| 貸家 | 家屋の評価額―(家屋の評価額×借家権割合 × 賃貸割合) |
| 預貯金 | 預入残高 + 既経過利息額(源泉所得税控除後の) |
| 上場株式 | ①、②のうち、最も少ない価額 ①相続開始日の最終価格 ②相続開始日の属する月以降3カ月間の毎月の 最終価格の月平均価格 |
| ゴルフ 会員券 (取引価格のある) | 取引価格 × 70% |
| 書画・骨董品 | 売買実例価額や精通者意見価額(プロの鑑定士 が評価した価額)を参考にして評価 |
| 一般動産 | 調達価額 |
✅評価方法の詳細 ⇒ 相続税の基礎知識

3 贈与税の課税方式 ~ 暦年課税と相続時精算課税
贈与税は、通常の場合、1年間において個人から贈与を受けた個人ごとに課税され
ます。 同一人から複数回贈与されたり、複数の贈与者から贈与を受ける場合もあります
が、その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産の合計額から、基礎控除額
の110万円を差し引き、その残額に対して一定の税率を掛けて贈与税額を算出し、翌年
の3月15日までに申告・納税しなければなりません。
年間110万円以下の贈与であれば、納税はもちろん、申告する必要もありません。
これが、「暦年課税」といわれる通常の課税方式です。
特例として、居住用不動産やその購入資金の贈与を受けた場合の贈与税の配偶者控除
と農地等の贈与を受けた場合の納税猶予があります。
さらに、住宅の取得や増改築などの資金については、満20歳以上の人が直系の父母
や祖父母から贈与を受けた場合には非課税措置も設けられており、大幅に緩和されてい
ます。ただし、これを利用するには申告することが条件となります。
✅暦年課税の「税率」「計算方法」「配偶者特別控除」の詳細はこちら
⇒ 「暦年課税」
この方式とは別に、贈与時に贈与税を申告納付して、贈与者の相続時においてすでに
贈与を受けた財産を含めて相続税の申告をして精算するという方式の課税があります。
これが「相続時精算課税」といわれる特別の課税方式です。
この「相続時精算課税」を選択した場合には、複数年にわたって適用できる特別控除
(2,500万円)があり、これを超えた部分については暦年課税の超過累進課税では
なく、一律20%の贈与税が課税されるというものです。
贈与者の相続時に相続税で精算(すでに納付した贈与税を相続時に計算した相続税か
ら控除)し、控除しきれない贈与税については還付されるということも、この制度の大
きな特徴です。
✅相続時精算課税制度における、「特別控除額」「制度の適用を受けるための要件」
「計算方法」等の詳細はこちら⇒「相続時精算課税」
◎暦年課税と相続時精算課税の選択のポイント
1.相続財産(贈与者の)を計算して相続税がかからない場合には、相続時精算課税
を選択することが有効
贈与財産を含めた相続財産の課税金額が、相続税の基礎控除額を超えなければ相
続税は課税されませんので、相続時精算課税選択して贈与税を支払ったとしても全額
還付されます。従って、節税を考える必要はありませんので、早めに贈与して財産分
与をすすめることができます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続時精算課税の特別控除額 2,500万円
※令和6年1月1日以降は、別に年110万円基礎控除枠が加わるので、
2,500万円+110万円=2、610万円
相続時精算課税を選択した場合の贈与税率 一律20%
2.相続税がかかる場合には、暦年課税を選択して節税を図る
相続税がかかる程度の財産がある場合には、相続時精算課税を選択して贈与時に非
課税であったとしても、相続開始時には贈与財産は全額相続財産に加算されますので
相続税の節税にはなりません。
これに対して暦年課税の場合には相続開始前3年以前の贈与財産については相続財産
に加算されませんので、その分だけ相続財産の減少となり節税できることになります。
暦年課税を採用して、より節税効果を高めるには、できるだけ早い時期から少しずつ
贈与することがポイントになります。ただし、連年贈与とみなされなような注意が必要
になってきます。

4 贈与税の納税義務者
贈与税は、原則として、贈与によって財産を取得した個人(受贈者)が納税の義務
を負いますが、受贈者が贈与税を納税しないときには、贈与者が納税しなければなりま
せん。
<贈与と税金>
贈与税は、個人から贈与によって財産を取得した個人に課税され、相続税と同様に、
個人に対する課税を建て前としています。 法人から、贈与によって個人が財産を取得
したときには、一時所得として贈与税ではなく所得税が課税されます。尚、同じ贈与
(契約)であっても、死因贈与によって財産を取得したときには相続の場合と同様、
相続税が課税されます。法人が、贈与によって財産を取得したときには、贈与者が法人
であっても個人であっても課税されるのは法人税です。
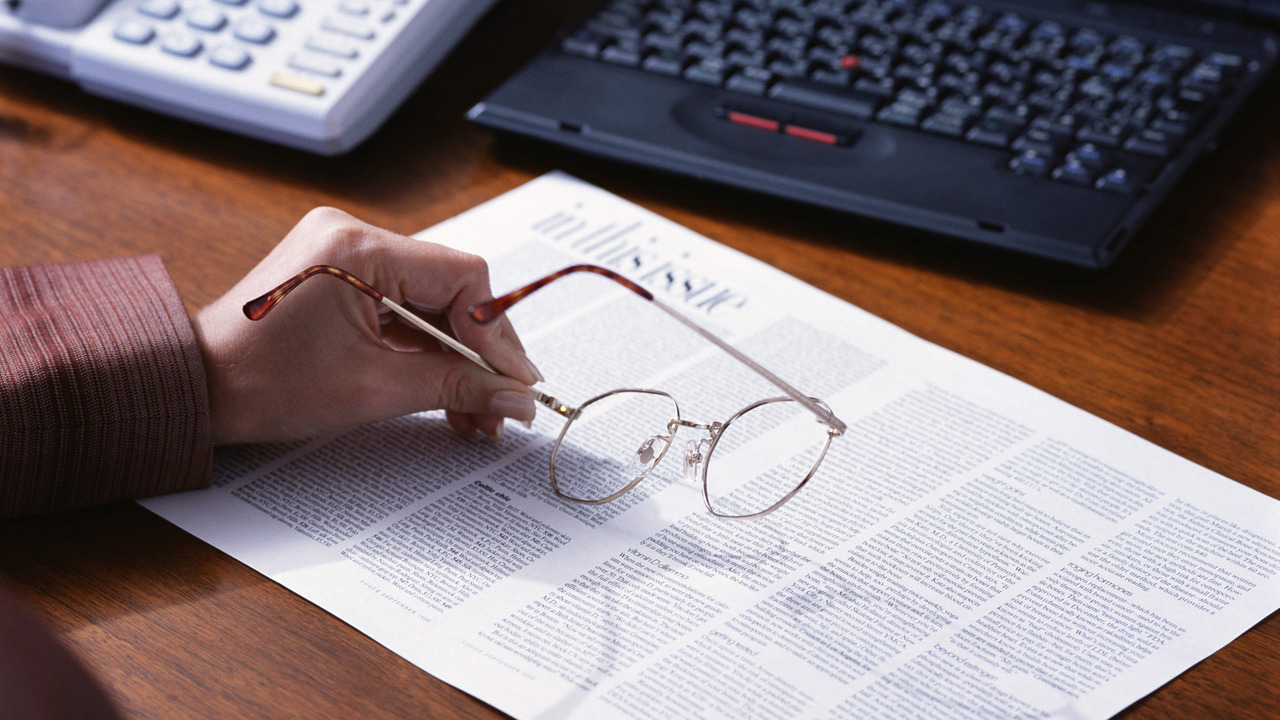
5 贈与によって財産を取得したとされる時期について
①書面による贈与 ⇒ 贈与契約書を締結した日
②口頭による贈与(口約束) ⇒ 贈与を履行した日
③停止条件による贈与 ⇒ 契約の条件が成就した日
④農地等の贈与 ⇒ 農地法の許可・届出の効力が発生した日
※贈与の日が明確でない場合には、税法上、所有権等の登記や登録があった日に贈与
されたものとして扱われて課税されます。

6 贈与税のかかる財産・かからない財産
<贈与税のかかる財産の種類>
1.本来の贈与財産
経済的価値のある財産(みなし贈与財産を除く)
現金、預金、土地、家屋、株式など
2・みなし贈与財産〜実質的に贈与とみなされるもの
①信託財産
②生命保険金(保険金受取人以外の者が保険料を負担していた場合で、相続税が課税
れたものを除く)
③信託受益権(適正な対価を負担することなく委託者以外の者が信託の受益者となる
とき)
④定期金
⑤財産の低額譲受(時価よりも著しく低い価額で買った場合など)
⑥債務の免除等(借金を免除されたり、誰かに支払ってもらったりした場合など)
⑦その他の利益享受(離婚した時にもらった財産のうちで、多すぎると認められるも
のなど)
⑧親族の名を借りて取得した財産
⑨代金の受け渡しの無い財産の名義変更
<贈与税のかからない財産> 非課税財産
次のようなものを贈与されても贈与税は課税されません。
①扶養義務者から生活費や教育費としてもらった、通常必要と認められるもの
・扶養義務者の関係〜「親と子」「夫と妻」「兄弟姉妹」「祖父母と孫」
・生活費〜食費・養育費・衣料費・住居費・治療費・水道光熱費など通常の生活を営
むために必要とされる費用
・教育費〜子供の教育に通常必要と認められる学費・教材費・文具等の費用
※名義上、生活費、教育費としてもらった現金を自分名義で預(貯)金したものや、
株などを購入したものについては非課税となりません。
②法人から贈与されたもの。ただし、一時所得として所得税が課税されます。
③離婚の時に分与された財産。ただし、多すぎると認められるもの、離婚を手段とし
たものとされるものを除く。
④香典・祝物・見舞金・中元・歳暮など社会通念上、相当と認められるもの。
⑤宗教・慈善・学術など公益を目的とする事業に供されるもの。
⑥心身障害者共済制度から共済金として受けるもの。

7 贈与税の申告と納税
(1)贈与税の申告・納税が必要な人
①1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた人で、贈与された
財産が110万円を超える人
②相続時精算課税の適用を受ける人
(2)税務署への申告期限
原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、「贈与税の
申告書」を提出し納税しなければなりません。申告期限までに申告書を提出しないと、
無申告加算税が課税されますので注意が必要です。
相続時精算課税を選択希望の人は、「贈与税の申告書」に「相続時精算課税選択
届出書」を添付して期限までに提出します。
期限までに提出しないと通常の暦年課税と扱われ、年
間の贈与額が110万円を超えると贈与税が課税されますので贈与額が大きい場合は
高額な金額となります。提出期限には充分注意してください。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ
<受付時間>
AM9:00~PM6:00
※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します
メールマガジン登録フォーム
フォーム準備中