岩手遺言・相続相談センター
田村行政書士事務所
岩手家系図作成センター
〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町高田11-22-43
受付時間 | AM9:00~PM6:00 |
|---|
定休日 | 土・日曜日、祝日 ※事前連絡の場合は 時間外・休業日でも対応します |
|---|


家系の調べ方、戸籍の取り方・辿り方
戸籍の請求の仕方と辿り方について!
先祖を200年以上さかのぼる方法について!
戸籍の取り方、辿り方編
(1)戸籍の請求の仕方 役所の窓口に出向くか郵送で請求する!
(2)戸籍の辿り方 戸籍が新しくつくられた原因をさがす!
(3)戸籍調査の後で、さらに先祖をさかのぼる方法
始祖の発祥地でヒアリング調査、文献・史料を探す!
時間はかかるが、見てみたい史料は無限!
(4)先祖を200年たどる戸籍調査と家系譜・家系図作成のすすめ
「家系譜」や「家系図」をつくれば、あなたの祖先がわかる!
戸籍調査の後で作成する「家系譜」や「家系図」は、200年以上
先祖をたどるための必要かつ基本資料!
✅先祖(戸籍)調査サービスのご案内 自分のルーツを知りたい方におすすめ!
✅家系図作成サービスのご案内
(1)戸籍の請求の仕方
必要とする人の本籍のある役所に請求する!
●戸籍の請求方法
①役所に出向いて請求する
➁役所が遠方の場合は郵送で請求する
●郵送で請求する場合に必要なもの
①戸籍謄抄本請求書〜役所のホ―ムペ―ジからダウンロ―ド
②交付手数料(例:戸籍謄本450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本750円)
※郵便局で交付手数料に見合う金額の「定額小為替」を購入して支払います。
※除籍謄本を一通請求するときは、額面が750円の「定額小為替」を購入する。
※郵便局で「定額小為替」を購入するときは、額面の多少にかかわらず一通につ
いて200円の手数料がかかります。
③返信用封筒〜返信先の住所・氏名を記入し、切手を貼って同封する
④請求者の本人確認書類(自動車免許証など、顔写真・住所の記載のあるもの)
⑤請求者とのつながりを示す資料(直系であることを認めてもらう資料)
例えば、曾祖父の除籍謄本を請求するときは、自分と祖父が記載されている父の
戸籍と、曾祖父が記載されている祖父の戸籍が必要になります。通常は、戸籍で
その関係がわかるページをコピ―したものでOK。
●戸籍謄抄本請求書の一般的必要記載事項
直系卑属(子や孫)のAさんが、父Bの戸籍を請求する場合
①本籍(父Bの本籍)
②筆頭者の氏名(父Bの氏名)
③請求者Aの住所・氏名・連絡先TEL
④請求者Aと父Bの関係(本人・配偶者・子・孫・父・母・祖父母・その他)
この場合は、父をチェックする(又は〇で囲む)
●誰の戸籍でも取れるか? 〜 特定の人の戸籍しか取れない!
戸籍を請求して交付を受けられるのは、戸籍に記載されている人及びその配偶者、
直系尊属、直系卑属だけです。
傍系にあたる人(例:叔父・叔母・甥・姪、その子や孫など)の戸籍は、傍系に
あたる人の直系尊属(父母・祖父母など)や直系卑属(子や孫など)の「委任状」
がなければ請求することができません。


(2)戸籍の辿り方
例えば、自分の苗字(例:父)につながる先祖を調べる場合、基本的には、次のよう
に、順に、モレなく、戸籍筆頭者の戸籍を請求していきます。
父 ⇒ 祖父 ⇒ 曾祖父 ⇒ 高祖父
この場合、直系尊属の「父」「祖父」「曾祖父」が戸籍筆頭者(又は戸主)ではなく
傍系尊属の叔父や大叔父が筆頭者(戸主)になっているときもありますが、次に請求する
戸籍の「筆頭者(戸主)名」と「本籍」は必ず記載がありますので、しっかりと確認した
上で請求しなければなりません。
このように、一人の戸籍を順にさかのぼっていくためには、入手した戸籍から、一つ
前の戸籍の本籍地と戸籍筆頭者(戸主)の情報を得て、その戸籍を取っていけばよいと
いうことです。
例えば、入手した戸籍から、この戸籍が改製によりつくられたことが分かった場合は
一つ前の戸籍は、同じ本籍地、同じ筆頭者(戸主)の「改製原戸籍」があることがわか
りますので、その「改製原戸籍」を請求します。
注意しなければならないのは、この「戸籍の改製」の記載があったときです。
例えば、改製前の戸籍で出生届が出されたが幼くして亡くなって除籍されたような場
合、その子については、改製後の新しい戸籍には移記されずに省かれてしまいます。
つまり、新しい戸籍には、改製当時に在籍する人だけが移しかえられますので、戸籍
をさかのぼるときは改製前の戸籍(改製原戸籍)は必ず請求するようにしないと、除籍
された人などの情報がモレてしまいますので注意が必要です。
「改製」以外にも、「戸籍が新しく作られる原因」がいろいろありますので、入手した
戸籍からその原因を発見して、順序よく、一つ一つさかのぼって請求していく必要があり
ます。これが、「戸籍をたどる」ということです。
【戸籍が新しく作られる原因】
①改製
※戸籍事項欄に、【改製日】・【改製事由】・【消除日】という表示があります。
一つ前の戸籍を請求する場合は、本籍と氏名(戸籍筆頭者)が同じ「改製原戸籍」
を請求します。
②家督相続(又は隠居)
※戸主の事項欄に、「〇年〇月〇日家督相続」戸主となりたる原因及び理由の欄に
「前戸主〇〇死亡(又は隠居)により、〇年〇月〇日家督相続」というように記載
されています。
一つ前の戸籍を請求する場合は、同じ本籍地の、死亡(又は隠居)した前戸主の
除籍謄本を請求します。
③婚姻・分籍
※「〇年〇月〇日婚姻(又は分籍)届出 本籍地 〇〇〇〇(戸籍筆頭者
又は戸主)より入籍」という記載されています。
一つ前の戸籍を請求する場合は、この戸籍に記載されている同じ本籍地の、同じ戸籍
筆頭者の除籍謄本を請求します。
④分家
※「(本籍地) 〇〇〇〇(戸主)弟分家届出〇年〇月〇日受付」という
記載があります。
一つ前の戸籍を請求する場合は、“弟分家”となっていますので、〇〇〇〇(戸主)は
兄か姉ということですので、同じ本籍地で、〇〇〇〇(兄又は姉)戸主の除籍謄本を
します。
⑤他市区町村への転籍
※「〇年〇月〇日、 (本籍)から転籍届出」という記載があります。
この場合は、同じ戸籍筆頭者で同じ本籍地の除籍があることになりますので、
その除籍謄本を請求します。
他市町村からの転籍が繰替えされ非常に多い戸籍も見られますが、この場合も、
情報に洩れが無いように、順序よく「転籍前の戸籍」を請求するようにしましょう。
同一管轄地域内での転籍の場合は、戸籍が新しく作り直されることはなく、消し線
で書き換えられているだけで新戸籍は編製されません。
2度、3度書き換えられている場合もありますが、書き換えられた順序はわかるよう
になっていますので、本籍地欄を注意して見ましょう。
このように、「戸籍のつながり」は、必ず双方の戸籍に相手の戸籍を示す記載があり
ますので、この「戸籍のつながり」をみて、一つ前の「戸籍を辿る」ことができるよう
になっています。わかりにくい場合もありますのが、注意深く見て請求するようにしま
しょう。
一つ前の戸籍、さらに一つ前の戸籍というように、どこまでも辿って請求していくと、
どこかで、「これ以上前の戸籍は保存されていないので発行できません」「〇〇〇〇様戸主
の戸籍は廃棄処分のため発行できません」「戦災(又は大火)により戸籍が焼失している
ため発行できません」という「証明書」などが役所から送られてきた時点で、戸籍の請求
は終了となります。
このように、どこまで古い戸籍が現存されているかは、実際にその役所に請求してみな
ければわかりませんので、まずはモレの無いように、丁寧に「戸籍が作られた原因」を見
ながら戸籍を請求することが、最古の戸籍まで辿れるかどうかのポイントになってきま
す。
そして、「これ以上古い戸籍はありません」というところまで請求できれば、200年
~220年程さかのぼって、戸籍上で目的の「家系」の状況を知ることが可能となりま
す。ただし、最古の戸籍までさかのぼって正確に請求できたとしても、その戸籍の中に、
直系尊属全員の「死亡年月日」が記載されていないこともありますので、「死亡年月日」
まで確認するためには、「新しく戸籍が作られた原因」を見て、さらに請求する必要が
ありますので注意が必要です。
家系の調べ方編⇒
(3)戸籍より、さらに先祖をさかのぼる方法
最古の戸籍を取って読み解くことによって、江戸期の天保・文政あたりまでは先祖を
さかのぼれる可能性がありますが、さらにその先を知りたい場合は、次のような調査方法
があります。
(1)現地でヒアリングを行う(総本家や親戚を探して聞く)
地元の図書館や郷土資料館を訪ねたり、教育委員会に聞くことも有効!
戸籍に記載された最古の本籍地に、親戚が住んでいれば手がかりがつかめる可能性
が高くなるので、実際に訪ねてヒアリングをする。
(2)菩提寺を探して訪ねる
お寺には檀家が亡くなった時に記載する「過去帳」や「お墓」、「墓誌」などを
見せていただく。
菩提寺とふだん付き合いがないような場合は、本家に同行してもらうことがよいで
しょう。
また、親戚で仏壇がある家にも「過去帳」が備えられていることが多いので、拝見
させていただければ有力な手掛かりとなります。
(3)史料を調査する(図書館・文書館・教育委員会から情報収集)
先祖が武士である可能性がある場合は、藩の名簿「分限帳」を、庶民の
場合は、「宗門人別帳」(庄屋や名主が作成した庶民名簿簿)を探してみる。
✅調査史料(参考文献など)、所蔵場所の探し方については、こちらをご覧ください!
家系の調べ方、戸籍の取り方・たどり方(家系の調べ方編)
✅誰でもできる自分のルーツの辿り方については、こちらをご覧ください!
(4)先祖の戸籍調査と家系図作成のすすめ
先祖を200年たどる戸籍調査の後で作成する「家系譜」や「家系図」は、
さらに100年、200年と先祖をたどっていくための基本資料となります。
戸籍の外にも、先祖をたどるための史料は無限にあると言われています。
家系譜や家系図が出来た後で、新しい発見のため、ゆっくりと、時間を
かけて史料を探し、どこまでも先祖をたどってみませんか?
全国対応 北海道〜沖縄
家系図作成サ―ビス
家系図作成実績 1800名様達成!(令和6年末)

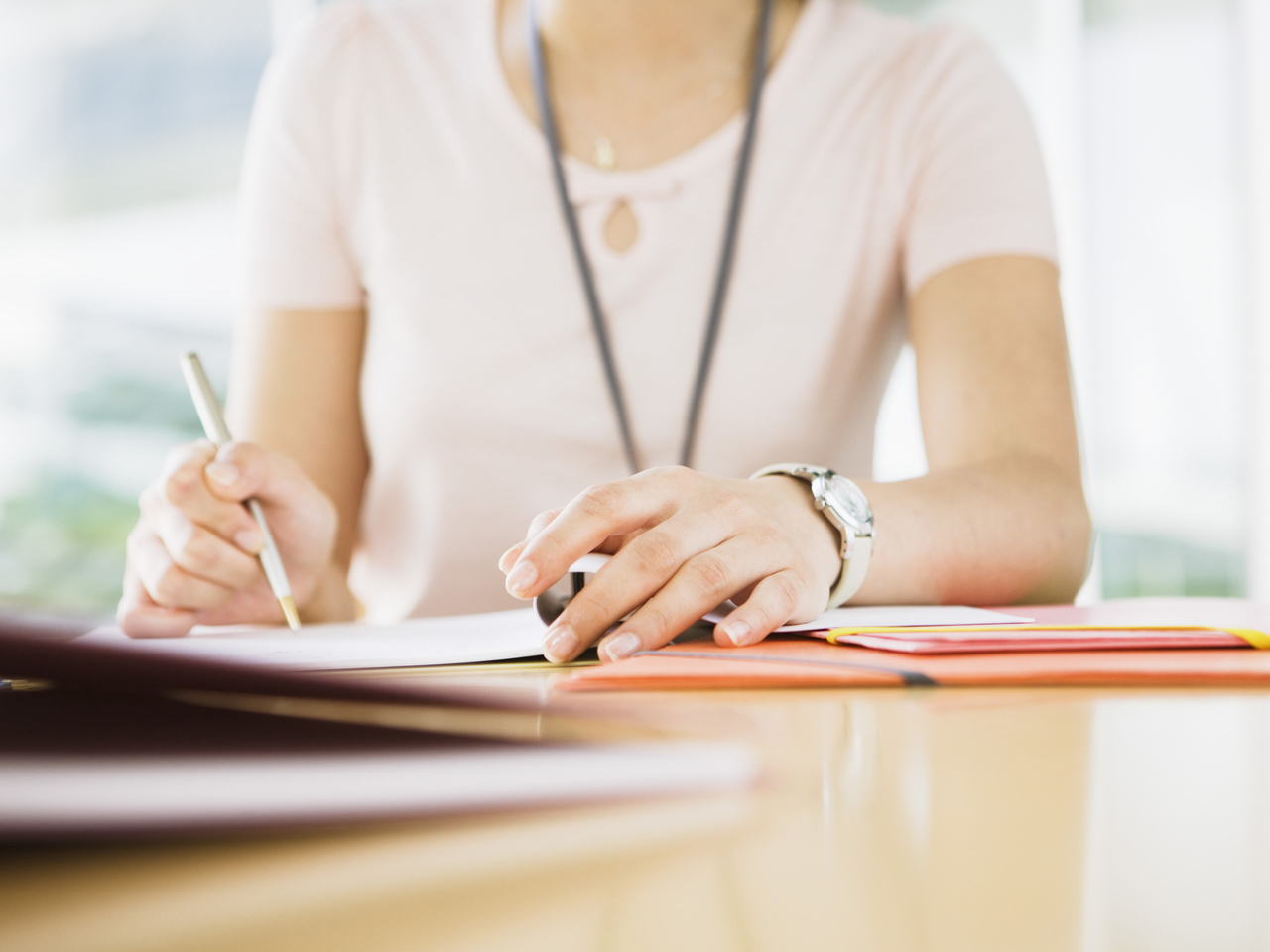
□家系図を作りたいと思っている方におすすめのサービス!
□プロのデザイナーが作成する家系図は、今、注目度NO1!
□先祖が生きてきた時代背景が詳細にわかる家系図が大好評!
全国対応 北海道〜沖縄
歴史ロマンを秘める
先祖調査サ―ビス
家系調査実績9000家系達成!(令和6年末)

□自分のルーツを知りたいと思っている方におすすめ!
□先祖供養をしたいと思っている方におすすめ!
□先祖の歴史を後世に伝えたいと思っている方におすすめ!
□両親への贈り物に、「家系譜(先祖の歴史)」は最適です!
✅電話・メールで資料請求・お問い合わせ
田村行政書士事務所
019−697−6841
tamura-gs@office.ne.jp
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ
<受付時間>
AM9:00~PM6:00
※土・日曜日、祝日は除く
※事前連絡の場合は時間外・休業日でも対応します
メールマガジン登録フォーム
フォーム準備中